おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!
![0_e3]()
“適者生存”というフレーズは、自然選択が絶対的なものであり、人間を強く、健康な存在にしてきたと思わせがちだ。だが現実にはそう単純な話ではない。
米デラウェア大学の古人類学者カレン・ローゼンバーグはこれについて語っている。「”適合”が酸素に適合したり、遠くまで走れるようになったりすることを意味していると思われていますが、進化生物学においての”適合”とは繁殖における成功を意味しています」。つまり遺伝子を次の世代に伝えられるだけの間生きることができればいいのだ。
繁殖において成功するために、自然選択は妥協を強いることがある。結果として、現代の人間は健康上の問題を抱えることになった。ここではそうした進化のせいで我々が悩まされることになった6つの問題を紹介しよう。
1. 腰痛![1_e4]()
二足歩行の誕生は人の進化において重要な出来事であった。直立して立つことで、遠くまで移動できるようになり、また空いた手で道具を利用したり、食料を運べるようになった。
チンパンジーなど四足歩行の親戚たちでは、脊柱が吊り橋のように機能している。しかし、そうした水平構造を垂直に傾ければ、たちまち不安定になる。
直立した生物の背骨を構造的に健全にしておく方法は、椎骨をまっすぐ積み重ねることだろう。しかし、それでは産道を塞いでしまい、種の生存を確保できなくなる。頭の大きな子供を出産するために、人間の背骨はカーブを描くように進化せざるを得なかった。その代償が腰痛、椎間板ヘルニア、圧迫骨折といった症状である。
2. 捻挫、骨折しやすい足![2_e3]()
人体は一から設計されたわけではなく、類人猿の祖先から解剖学的構造を受け継いでいる。足がその好例である。
我々が二本足で立つようになると、祖先が木を登り、枝を掴むために必要としていた柔軟な足は要らなくなった。
大地でより安定して立つために、進化は”クリップとガムテーム”アプローチを採用した。こうして捻ったり、回転させたりするのに都合がいい猿の足を改造したもので歩かなければいけなくなったために、足首の捻挫や骨折をしやすくなってしまった。脛に添え木を当てたり、足底に炎症を起こしたり、アキレス腱を切ったりするのもこのためだ。
3. 難産![3_e4]()
他の類人猿と比べて人間が難産なのは、胎児の頭と肩幅の割に骨盤が非常に狭いからだ。骨盤の形状は歩行と出産の妥協の産物なのである。
しかし人間は長く苦しい出産に対して面白い文化的な回答を用意した。ほとんどの哺乳類にとって出産とは単独で行う行為であるが、事実上ほぼすべての人間の母親は親族、助産婦、医師といった他人からの介助を求めるようになったのである。
ある論文では、自然選択は他人の介助を好んだようであると論じている。おそらくは妊婦による意識的な決定ではない。むしろ恐怖、不安、苦痛といった要因に起因するのだろうが、長い目で見るとこれが死産率を減らす結果につながったという。
4. ジャンクフードが好き![4_e3]()
ファストフードやスナック菓子を止められないことには十分な理由がある。糖質はエネルギーの基本であるが、余分な糖質は脂肪として蓄えられる。
農業や工業化が進む以前の食料が乏しく、供給が不安定だった時代、糖質の甘みは生存に不可欠なものであった。しかし現代ではスーパーに行けば加工された糖がすぐに手に入る。こうして食べ過ぎによる肥満が蔓延し、糖尿病や高血圧が増えた。
食品業界が大きな利益を上げることができるのは、石器時代のままの体が糖を求めるからである。だが現代は糖が安く、大量に手に入る宇宙時代。大きなボトルでの清涼飲料水の販売を禁止して、狩猟採集社会の状況を取り戻そうという意見すらある。
5. 精神病
![5_e4]()
自然選択は、統合失調症やうつ病のような、出生率の低下に結びつく潜在的に危険な状態を排除しなかった。一説によると、この状況は精神病を患った患者の親族であるが、症状を発症していない人に原因があるそうだ。彼らが突然変異を子供に遺伝させることで、遺伝子プールの中に病気が蓄えられる結果となった。
また精神病の起源に着目する説もある。それによると、一見有害そうな病気であるが、進化上の利点があったのだという。例えば、うつの症状として不活発になることが挙げられるが、これは同時に思考の分析的な傾向を強め、問題解決に役立った可能性がある。さらに統合失調症に関連する遺伝子が複雑な認知を助けている可能性を指摘する専門家もいる。
6. 親知らず![6_e2]()
直立歩行をするようになった人間は、別の変形も遂げることになる。脳が異常に大きくなったのだ。大きな脳を保持するために顔の形が変化し、顎は狭くなった。これによって、かつて咀嚼で大きな役割を果たしていた親知らずが生えてくる隙間がなくなってしまう。抜かずに放っておくと、ズキズキと痛み、感染症を引き起こすこともある。
しかし自然選択は現在でも続いている。親知らずが生えることを防ぐ遺伝子の突然変異が広まり、親知らずが生まれつきない人が増えているのだ。
via:6 Downsides of Human Evolution
☆長生きが問題やと思うねんけど!
おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

“適者生存”というフレーズは、自然選択が絶対的なものであり、人間を強く、健康な存在にしてきたと思わせがちだ。だが現実にはそう単純な話ではない。
米デラウェア大学の古人類学者カレン・ローゼンバーグはこれについて語っている。「”適合”が酸素に適合したり、遠くまで走れるようになったりすることを意味していると思われていますが、進化生物学においての”適合”とは繁殖における成功を意味しています」。つまり遺伝子を次の世代に伝えられるだけの間生きることができればいいのだ。
繁殖において成功するために、自然選択は妥協を強いることがある。結果として、現代の人間は健康上の問題を抱えることになった。ここではそうした進化のせいで我々が悩まされることになった6つの問題を紹介しよう。
1. 腰痛
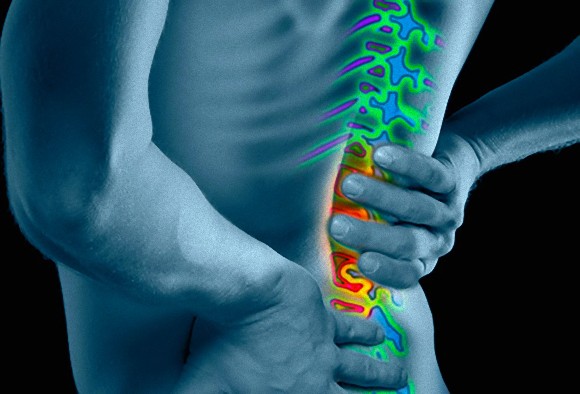
二足歩行の誕生は人の進化において重要な出来事であった。直立して立つことで、遠くまで移動できるようになり、また空いた手で道具を利用したり、食料を運べるようになった。
チンパンジーなど四足歩行の親戚たちでは、脊柱が吊り橋のように機能している。しかし、そうした水平構造を垂直に傾ければ、たちまち不安定になる。
直立した生物の背骨を構造的に健全にしておく方法は、椎骨をまっすぐ積み重ねることだろう。しかし、それでは産道を塞いでしまい、種の生存を確保できなくなる。頭の大きな子供を出産するために、人間の背骨はカーブを描くように進化せざるを得なかった。その代償が腰痛、椎間板ヘルニア、圧迫骨折といった症状である。
2. 捻挫、骨折しやすい足

人体は一から設計されたわけではなく、類人猿の祖先から解剖学的構造を受け継いでいる。足がその好例である。
我々が二本足で立つようになると、祖先が木を登り、枝を掴むために必要としていた柔軟な足は要らなくなった。
大地でより安定して立つために、進化は”クリップとガムテーム”アプローチを採用した。こうして捻ったり、回転させたりするのに都合がいい猿の足を改造したもので歩かなければいけなくなったために、足首の捻挫や骨折をしやすくなってしまった。脛に添え木を当てたり、足底に炎症を起こしたり、アキレス腱を切ったりするのもこのためだ。
3. 難産

他の類人猿と比べて人間が難産なのは、胎児の頭と肩幅の割に骨盤が非常に狭いからだ。骨盤の形状は歩行と出産の妥協の産物なのである。
しかし人間は長く苦しい出産に対して面白い文化的な回答を用意した。ほとんどの哺乳類にとって出産とは単独で行う行為であるが、事実上ほぼすべての人間の母親は親族、助産婦、医師といった他人からの介助を求めるようになったのである。
ある論文では、自然選択は他人の介助を好んだようであると論じている。おそらくは妊婦による意識的な決定ではない。むしろ恐怖、不安、苦痛といった要因に起因するのだろうが、長い目で見るとこれが死産率を減らす結果につながったという。
4. ジャンクフードが好き

ファストフードやスナック菓子を止められないことには十分な理由がある。糖質はエネルギーの基本であるが、余分な糖質は脂肪として蓄えられる。
農業や工業化が進む以前の食料が乏しく、供給が不安定だった時代、糖質の甘みは生存に不可欠なものであった。しかし現代ではスーパーに行けば加工された糖がすぐに手に入る。こうして食べ過ぎによる肥満が蔓延し、糖尿病や高血圧が増えた。
食品業界が大きな利益を上げることができるのは、石器時代のままの体が糖を求めるからである。だが現代は糖が安く、大量に手に入る宇宙時代。大きなボトルでの清涼飲料水の販売を禁止して、狩猟採集社会の状況を取り戻そうという意見すらある。
5. 精神病
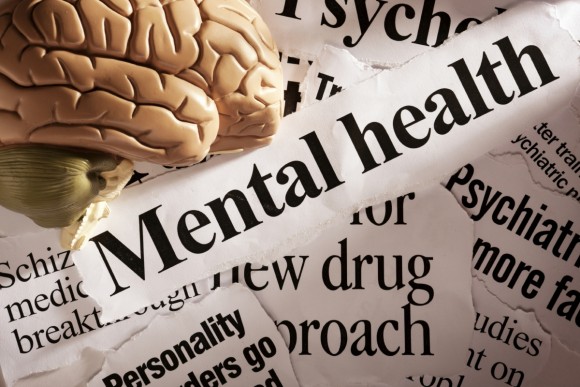
自然選択は、統合失調症やうつ病のような、出生率の低下に結びつく潜在的に危険な状態を排除しなかった。一説によると、この状況は精神病を患った患者の親族であるが、症状を発症していない人に原因があるそうだ。彼らが突然変異を子供に遺伝させることで、遺伝子プールの中に病気が蓄えられる結果となった。
また精神病の起源に着目する説もある。それによると、一見有害そうな病気であるが、進化上の利点があったのだという。例えば、うつの症状として不活発になることが挙げられるが、これは同時に思考の分析的な傾向を強め、問題解決に役立った可能性がある。さらに統合失調症に関連する遺伝子が複雑な認知を助けている可能性を指摘する専門家もいる。
6. 親知らず

直立歩行をするようになった人間は、別の変形も遂げることになる。脳が異常に大きくなったのだ。大きな脳を保持するために顔の形が変化し、顎は狭くなった。これによって、かつて咀嚼で大きな役割を果たしていた親知らずが生えてくる隙間がなくなってしまう。抜かずに放っておくと、ズキズキと痛み、感染症を引き起こすこともある。
しかし自然選択は現在でも続いている。親知らずが生えることを防ぐ遺伝子の突然変異が広まり、親知らずが生まれつきない人が増えているのだ。
via:6 Downsides of Human Evolution
☆長生きが問題やと思うねんけど!
おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!